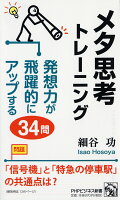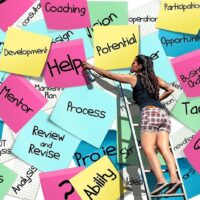記事内に広告が含まれています
「メタ思考と抽象化、何がどう違うのでしょうか?」もし、そう質問されたら、答えることができるでしょうか。
よく使われる言葉ですが、実は私、上手に説明できません。それにもかかわらず、少し理解したくらいで、「抽象度を上げて考えなよ」なんて台詞をえらそうに使っておりました。抽象化についても、『共通点探しにより問題解決に役立つ』程度しか説明できないレベルです。
そこで、メタ思考および抽象化について、意味の違いを理解し自分の言葉で説明できるようになること、メタ思考や抽象化を使いこなし思考法の幅を広げ、アイデア出しや問題解決が今以上にできるようになることを目的として、目的がかなうために参考になりそうな本を探していたところ、なかなかの良書が見つかったので紹介いたします。
「メタ思考トレーニング」です。
目次
メタ思考トレーニング:メタ思考や抽象化の重要性

1つ上の視点で考える3つの意味
『メタ思考』や『抽象化』がなぜ重要なのか。本書の「はじめに」を読むと理由が3つ語られています。
①私たちが成長するための「気づき」を得られる
②思い込みや思考の癖から脱する(視点が広がる)
③上記2つの「気づき」や「発想の広がり」を基にした創造的な発想ができる
良いサービスが生まれるのは、この3つのおかげといっても過言ではないでしょう。思い込みや狭い視点で良いサービスが生まれるはずはなく、視点を広げ、新しい発想があるから、良いサービスが誕生すると思うのです。
また、以前別の記事で紹介させていただいた「成人発達理論による能力の成長」という本でも、抽象化の必要性は説明されておりますので、いくつか引用させていただきます。
しかしながら、「抽象的」という言葉の本質は、「曖昧なもの」を意味する言葉ではありません。むしろ「抽象的」というのは、「木を見て森を見る」という言葉が示すように、全体を把握することを意味します。
成人発達理論による能力の成長(P168)より
抽象的なレベルで物事を把握する力というのは、複雑なものに対処するために必要な力だと言えます。そして重要なことは、複雑なものに対処する際に、私たちは、常にその複雑性よりも一段上の能力レベルがなければならない、ということです。「いかなる問題も、それが生み出された時と同じレベルで発想していては解決できない」というアインシュタインが残した名言は、まさにそのことを指摘しています。
成人発達理論による能力の成長(P169)より
抽象的なレベルで思考ができることには、その他にも「再現性をもたらす」という重要な点があります。端的に述べると、「抽象性」が高まるというのは、実際の現場での「再現性」が高まるということを意味します。
成人発達理論による能力の成長(P172)より
抽象化することが、なぜ重要なのか。それは、創造的な発想ができるだけでなく、複雑な問題を解決したり、他で再現することができるからなのです。「実際の現場での「再現性」が高まる」というのがポイントです。
しかし、重要だからと言っても、『メタ思考』や『抽象化』という言葉の意味を理解していなければ、それぞれの思考法を正しく利用できません。
「抽象化して考えて」と言っておきながら、「抽象化って何ですか」と質問されて答えらないようでは、相手に抽象化思考をお願いすることもできないのです。
メタ思考やメタ認知、言葉が似ていて違いがよくわからない
自分の言葉で説明できるようになるためには、難解な『メタ思考』や『抽象化』という言葉の意味を、どれだけわかりやすくできるかがポイントになりそうです。例えば、メタ思考については、メタ認知という似た言葉があります。「メタ思考、メタ認知、抽象化、一般化」、どれも似たような意味として使われており、非常に混乱しますね。
そこで、今回は、いい機会として頑張って整理してみたいと思います。
メタ思考とは
まず『メタ認知』を、ウィキペディアで調べてみましょう (メタ認知 wiki)
自己の認知のあり方に対して、それをさらに認知することである。(2019年4月現在)
この説明は、わかりやすいとは言えるでしょうか。「認知」こんな専門的な言葉は、わかりづらい表現のため即理解というわけにはいきません。
では、『メタ認知』は一旦横に置いておいて、『メタ思考』について、本書20ページから引用してみましょう。
メタ思考とは、自らの視点を一つ上げて、自らが思考に関してある壁に閉じ込められた「とらわれれの身」になっていることに気づくことです。
そのために本章では、まず自らの思考の偏りや視点の低さをチェックし、自らをもう一つ高い視点(メタの視点)で見ることから始めます。メタ思考トレーニング(P20)より
ウィキペディア先生の『自己の認知』は、本書の『自らの思考』と同じ意味、同様に、『さらに認知する』と『一つ上の視点から見る』も似たような意味です。
つまり、『メタ認知』と『メタ思考』は、意味が似た言葉というより同じ意味の言葉として整理できます。
そこで、上記のウィキペディアの説明を引用して、『メタ思考』の説明を具体例をあげて説明してみましょう。次のようになるのではないでしょうか。
自己の認知のあり方に対して、それをさらに認知することである。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「俺は犬が好きだ」という自分の思考(認知)に対して、「何故『俺は犬が好き』なのだ」と認知することが『メタ思考』である。
メタ思考は一つ上の視点で見ることでした。つまり、上記のように「メタ認知」の説明を引用して「メタ思考」を説明ても、一つ上の視点から見るという感覚は変わっておりません。
従いまして「メタ思考とは」について私の言葉で表現した場合、一つ上の視点で自分の考えを見る、つまり自分のことを他人ごとのように客観視してみる。このように説明することになります。
抽象化とは
次に、抽象化について、ウィキペディア先生で確認してみましょう (抽象化 Wiki)
対象から注目すべき要素を重点的に抜き出して他は無視する方法である(2019年4月現在)
またもや、意味がよくわかりません。他は無視するとはどういうことでしょう。抽象化の説明が抽象的であり困ったものです。
では、「抽象化とは」について、本書97ページからも引用してみます。
抽象化とは、複数の具体的な事象に高次の共通点を見つけて一般化することです。
メタ思考トレーニング(P97)より
やはりわかりづらく、モヤモヤします。しかも「一般化」という似た言葉も出てきましたので、余計に混乱しましたので、goo国語辞書で意味を調べてみましょう (一般化 goo国語辞書)
さまざまな事物に共通する性質を抽象し、一つの概念にまとめること
やれやれ、『抽象化』も『一般化』も説明がほぼ同じではないですか。
上記の本書(P97)からの引用文の場合、「抽象化とは~一般化することです」とありますが、言い換えれば「抽象化とは~抽象化することです」と言っているのと同じことです。こういうところが、メタ思考関連の用語で、混乱するところです。
とりあえずここでは、goo国語辞書を参考にして『一般化』という言葉を「ひとつの概念にすること」と整理します。ひとつの概念ですから、私と他の誰かの間で同じような解釈になるはずです。例えば『男』という言葉が一般化した言葉であるならば、私と他の誰かの間で『男』という言葉の意味は、ほぼ同じ解釈になるはずなのです。
『一般化』は整理できましたので、抽象化に話を戻しますと、ウィキペディアの説明『複数の具体的な事象に高次の共通点』と本書の説明『さまざまな事物に共通する性質』から、「複数の対象から共通点を探すこと」というのが『抽象化』について簡単な説明として導びかれると思います。
そこでまとめとして、『ひとつの概念にすること』=『一般化』、「複数の対象から共通点を探すこと」=『抽象化』として定義します。
そこであらためて『抽象化』の説明を具体例をあげて説明するとするならば、以下のようなものになるかと思われます。
「犬」と「猫」の共通点(抽象化)は両方とも「動物」だということです。つまり、高次の(メタ)の共通点が「動物」なので、犬と猫は「動物」として一般化(ひとつの概念化)できます。
「メタ思考とは」と「抽象化とは」を自分の言葉で説明する

では、『メタ思考』や『抽象化』についてこれまで整理できたことを自分の言葉で説明してみます。
■「メタ思考」とは
「俺は犬が好きだ」という自分の思考(認知)に対して、「何故『俺は犬が好き』なのだ」と客観視することが『メタ思考』です。
■「抽象化」とは
「犬」と「猫」の共通点は両方とも「動物」だということです。つまり、一つ上の共通点が「動物」なので、犬と猫は「動物」として一般化できます。このように、「犬」と「猫」といった別々の事物の共通点をひとつの概念にまとめることを『抽象化』と言います。
このようになるわけですが、この説明は具体例を含めた説明であり、一般化された説明ではございません。そこで、実際の現場での「再現性」が高まる一般化した言い方に変換すると、次のように言い換えることができます。
■「メタ思考」とは
「『ある思考』を『なぜある思考なのだ』」と一つ上の視点から客観視する思考法のことを『メタ思考』と言います。
■「抽象化」とは
複数の具体的なものを上位概念で共通点を見つけて、1つの概念でまとめることを『抽象化』と言います。
このように一般化してみました。一般化することで再現性があるなら、具体的な事物を用いて説明できるはずです。
■「メタ思考」とは
「『俺は女が好きという考え』を『なぜ俺は女が好きなのだ』」と一つ上の視点から客観視する思考法のことを『メタ思考』と言います。
■「抽象化」とは
「女」と「男」には「人間」という共通点があります。このように「人間」という概念でまとめることを『抽象化』と言います。
このように再現できます。(具体例が簡単すぎなのはお許しください)
このような表現になりましたが、『メタ思考』や『抽象化』についての説明が、自分の言葉でできるようになりました。実際に、ここまで読んでくださった方にわかりやすく伝わったかどうかわかりませんので、もっとわかりやすく説明する言葉があるかどうか、今後も模索していきたいと思います。
メタ思考のための2つの方法とは?

せっかくですから、『メタ思考』や『抽象化』という思考方法を鍛えたいものです本書では次の2つのトレーニング方法が紹介されています。
・『上位目的を考える』ための『Why型思考』
・『抽象化する』ための『アナロジー思考』
Why型思考
上位目的を考える『Why型思考』とは何か、簡単に言えば、「なぜ?」と考えることです。詳細については、本書をお読みいただければと思いますが、『Why型思考』の例を一つあげてみたいと思います。
質問:「この間の飲み会、時間が短かったね」という発言に対し、どのように対応しますか?
「よし、次からは時間を長くしよう」と考えたとします。それは、対応として正しいと言えるでしょうか。実は、決して正しいとは言えないのです。この言葉に対し、何故?(why)と疑問を持つことでわかります。それが『Why型思考』です。
何故、「時間が短い」と発言したのだろう?
・誰か特定な人と話せなかったのかな、話が足りなかったのかな?
・飲み足りなかったのかな?
・忙しくて送れてから参加したのかな?
・楽しかったという意味かな?
このように「なぜ?」と考えれば、さまざまな理由が浮かびます。
もし、特定の人と話足りなかったことが発言の理由であるならば、前述の『時間を長くする』ことは解決策になりません。特定の人と話す機会を作ってあげることが解決策になります。楽しいと感じたことが発言の理由なら、次の機会でも、同じ方針で企画してあげればよいことになります。
この例のように、なぜ(=why)という問いに対する回答によって解決策が違ってくるわけですから、『Why型思考』することが、どれだけ重要であるかがわかりますね。
アナロジー思考
『抽象化する』ための『アナロジー思考』とは何でしょう。ヒントは、Wコロンのねずっちです。(ご存じでなかったらすみません)
ここも理屈的なことは、本書をお読みいただければと思いますが、『アナロジー思考』について例を1つあげてみたいと思います。
①「相撲」と掛けて「花見」と解く。その心は?
少し考えてみましょう。共通点探し(抽象化)してみてください。
・
・
・
わかりましたか?
正解は、『どちらも「せきとり(関取、席取り)」が必要です』になります。相撲と花見という具体的な事物を「せきとり(関取、席取り)」という共通点でまとめました。
このような「抽象化」+「具体化」する思考が、アナロジー思考です。
このアナロジー思考は、ビジネス含むさまざま場面で使えますよというのが、本書の言いたいことでしょう。トレーニングのパターンがたくさん紹介されてます。一つ一つが非常に勉強になりますし、その思考方法に慣れ使いこなせるようになれば、自分にとっての武器になること間違いなしでしょう。
メタ思考トレーニング:まとめ

今回の紹介で、本書が語るメタ思考の良さを紹介しきれているとは思ってませんので、是非お読みいただき、メタ思考のトレーニングを実感してほしいと思います。トレーニングですので都度考えながらだと、読書テンポはよくないですが、頭のリフレッシュにはよいと思います。
自分を成長させたいと勉強されている方は、『メタ思考』や『抽象化』思考を鍛えれば、発想力も問題解決力も大幅にアップすると思われますので、トレーニングしてみてはいかがでしょうか。